プロが警鐘!「争族」化する日本の相続事情と遺言書のチカラ
現代の日本は超高齢社会を迎えており、それに伴い相続に関するトラブルが年々増加しています。
裁判所の司法統計によると、遺産分割調停の件数は、2000年の8,899件から2023年には13,872件へと大幅に増加しています。この統計が示すように、相続をめぐる家族間の話し合い(遺産分割調停)が難航するケースは増える一方です。
こうしたトラブルを未然に回避し、残されたご家族が円満に手続きを進めるために、最も確実な方法の一つが「遺言書を法律に則って作成すること」です。本記事では、遺言書が無効とならないための具体的な注意点や、利用すべき遺言書の形式について詳しく解説します。
「遺書」と「遺言書」は全く別物!作成が義務となる「3つの境界線」
遺言書とは、ご自身の死亡後の財産を「誰に、どのように分配するか」を書き記した文書です。本人が亡くなった後に効力を発揮するため、法律によって様式が厳密に決められており、規定通りに作成しなければその意思が確実に実行されることはありません。
単に気持ちを伝える手紙である「遺書」とは異なり、遺言書には法的な効力があります。
遺言書に記載できる内容には、相続に関する事項(財産の相続割合の指定、法定相続人以外への遺贈、相続人の廃除や取り消しなど)や、身分に関する事項(婚外子の認知、未成年後見人の指定など)などが定められています。
特に遺言書の作成が必須となるのは、以下のような「3つの境界線」を超えるケースです。
1. 家族間でのトラブルが予想される場合
相続財産に不動産が含まれる場合や、そもそも相続関係が複雑な場合、遺産分割協議で相続人同士が争い(トラブル)になるリスクが高まります。遺言者(被相続人)が「誰に、何を相続させるか」を事前に明確に決めておくことで、トラブルに発展するリスクを低くできます。
2. 法定相続人以外に「感謝の財産」を贈りたい場合
法律上の相続権は、配偶者、直系卑属(子供や孫)、直系尊属(親や祖父母)、兄弟姉妹などに限定されています。例えば、法律上の相続権がない息子の配偶者に、介護の感謝として財産を残したいと思っても、遺言書に記載しなければ、その意思は実現できません。
3. 相続人が「ゼロ」または「行方不明」の場合
法定相続人が一人もいない場合、残った財産は最終的に国庫に帰属します(民法959条)。これを避けたい場合は、遺言書を残す必要があります。
また、相続人の中に行方不明者がいると、遺産分割協議自体を開くことができません。この場合、裁判所に失踪宣告や不在者財産管理人の選任を申し立てるなど、複雑な手続きが必要になりますが、遺言書があれば協議が不要となり、スムーズに遺産を相続させることができます。
確実性で選ぶ!あなたの想いを守り抜く「3つの遺言スタイル」徹底比較
遺言書には、一般的に使われる「普通方式遺言」(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と、特殊な状況下で作成する「特別方式遺言」があります。
遺言書の種類によって、法的な効力の違いはありませんが、効力を発揮するまでの確実性や手間に大きな違いがあります。
| 遺言スタイル | 作成形式 | 費用(目安) | 確実性/リスク | 検認の要否 |
|---|---|---|---|---|
| 自筆証書遺言 | 遺言者本人が自筆 | 作成は無料。法務局保管利用時は3,900円 | 手軽だが、紛失・偽造・形式不備で無効のリスクあり | 原則必要(法務局保管制度利用時を除く) |
| 公正証書遺言 | 公証人が作成 | 5,000円〜50,000円程度(財産額で変動) | 最も確実性が高い。公証役場での保管により紛失・偽造なし | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 遺言者が署名・押印し、公証人らが証明 | 11,000円(定額) | 内容は秘密にできるが、公証人が内容を確認しないため、不備で無効になるリスクがある | 必要 |
確実な執行を求めるなら「公正証書遺言」
公正証書遺言は、公証人がパソコンで文書化するため、書類上の不備で無効になるリスクが低く、トラブルになる可能性も軽減されます。また、公証役場で保管されるため、紛失の心配もなく、検認手続きも不要で即時に効力を発揮するため、最も確実性が高い方法とされています。
自筆証書遺言を選ぶ際の落とし穴
自筆証書遺言は手軽ですが、全文、日付、氏名を自筆で書くことが民法968条で定められています(代筆は無効)。
ただし、財産目録については、2019年の法改正により、パソコンで作成した書面や預金通帳のコピーの添付が認められています(この場合、各ページへの署名と押印が必要です)。
ゼロから学ぶ!「形式不備」で無駄にしないための【無効回避の5大鉄則】
遺言書を作成する際は、ご自身の最後の意思表示を正確に実現するために、以下の5つの注意点(鉄則)を厳守する必要があります。
鉄則1:法律で定められた「表現の形式」を守る
遺言書の形式は、偽造や改ざんを防ぐ目的で法律で厳密に決められています。
- 日付の特定: 日付が特定できない表現は無効となります。たとえば、「令和〇〇年三月吉日」といった記述は、日付が特定できないため無効になります。
- 訂正時の注意: 訂正が必要になった場合、正しい方法に沿って訂正しないと、元の文言が有効になってしまいます。手間を避けるためにも、最初から書き直す方が賢明です。
鉄則2:推定相続人を正確にリストアップする
遺言書を作成する際には、自分が亡くなった場合に「誰が相続人になるのか(推定相続人)」を明確にしておく必要があります。この推定相続人に漏れがあった場合、遺言書が無効になるケースもあるため、正確なリストアップが重要です。
鉄則3:特別受益と遺留分を必ず考慮する
以下の2つの概念を考慮せずに財産分配を指定すると、後々、遺族間のトラブルや訴訟の原因になります。
- 特別受益(生前贈与など): 被相続人から生前に受けた利益を指し、相続開始時にこの分を差し引いて相続分が決定されます。
- 遺留分(最低限守られる権利): 法定相続人が最低限受け取ることのできる、法律で定められた一定割合の財産です。遺言書に「財産の全額を慈善団体に寄付する」と書いても、配偶者や子供がいる場合、遺留分を侵害する部分は無効になります。遺留分を侵害された相続人は、財産を受け取った人に対して金銭(遺留分侵害額)を請求できます。
鉄則4:作成したら終わりではない!「更新と安全な保管」に留意する
遺言書は一度作成しても、年月が経つにつれて、財産の内容(銀行口座の解約など)や相続人が変動することがあります。また、遺産の分配方法について考えが変わることもあるため、定期的な見直しと書き換えを検討しましょう。
自筆証書遺言の場合、費用はかかりませんが、死後に発見されない、または偽造・紛失するリスクという「保管方法の難しさ」があります。これを回避するため、法務局が遺言書を保管する「自筆証書遺言書保管制度」の利用を検討することで、安全な保管と検認手続きの省略が可能です。
鉄則5:遺言の実行責任者(遺言執行者)を指定する
遺言執行者とは、遺言書の内容通りに財産が分配されるよう、必要な手続き(財産の調査、預貯金口座の解約、相続登記など)を行う権限を持つ人です。
特に、推定相続人の廃除(相続権の剥奪)や、生前に認知できなかった婚外子の認知を遺言で行う場合などには、遺言執行者の指定が必須となります。
遺族に「安心」を託す。終活としての遺言書作成とプロのサポート
遺言書作成に関する知識を身につけ、注意点を遵守することは、ご自身の遺志を正確に伝えるために不可欠です。そしてそれは、残されたご遺族の精神的・手続き的な負担を大きく軽減し、未来に安心感をもたらすことにつながります。
遺言書の作成をはじめ、終活を本格的に進めていくと、やるべきことが次々と出てきて疲弊してしまう恐れもあります。
遺言書の作成や終活全般について、専門家の協力が必要な場合は、司法書士や弁護士へご相談ください。公正証書遺言の作成サポートなど、幅広い内容の相談に対応しています。
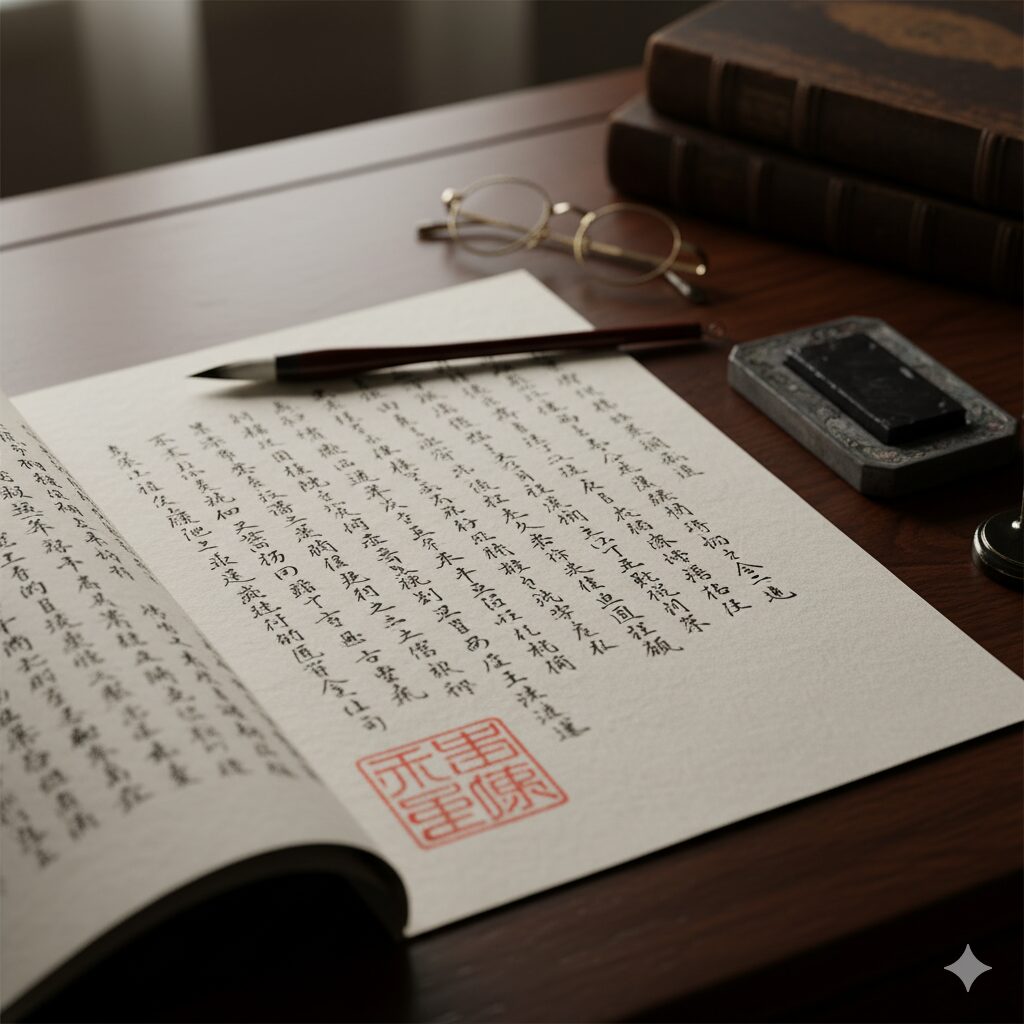


コメント